6つのStory【邂逅 〜 矢野麻紀子・宮城景花 二人展】

「邂逅(かいこう)〜矢野麻紀子・宮城景花 二人展」より、6つのStoryをお楽しみください。

一番ホッとできる場所、それは「おかえり」が聞こえる場所なのかもしれない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 「泥んこ」 by Keika Miyagi
「泥んこ」 by Keika Miyagi
その時に、必ず必要なのが「王冠」。
大概は大人が飲んでいるビール瓶の王冠で、大人が栓を抜いたらすかさず袋の中に入れる。
「ビーコロ」と呼んでいたその遊びのために、袋にじゃらじゃらと貯めている王冠は子どもたちの宝物だった。
砂場のビーコロのルートには、王冠がいくつも埋められている。初めはスタート地点に表面を出して埋めた王冠。そこにビー玉を上からコンと当ててレースはスタートする。
勢いがうまくつかないと、途中の裏返した王冠の中にビー玉が入ってしまう。そうするとその玉はビーコロの台を作ったチームに取られてしまう。
今考えてみればなかなかヤクザな遊びだったと思うんだけれども、とにかく小学校の時の放課後で、1番心が躍った思い出は、そのビー玉転がしの遊びだった。
水でどろどろになった砂場。ビーコロの終わりに、みんなでぐちゃぐちゃに壊す時の開放感。
家へ帰る途中の車道には、石蹴りの枠が白墨でいくつも描かれていたし、ゴム飛びの数を数える声は暗くなるまで響いていた。
商店街には小さい子も大きい子もひしめき合っていて、いつでも子供は泥だらけだった。
それから30年以上が経ち、私たちの子どもたちは保育園で泥だんごというものを作っていた。
土に水を混ぜて固めていき、両手一杯の球体を作って磨き上げる。
園庭で走り回ったり転んだり、少年野球のグラウンドでは子どもだけでなく大人まで泥だらけだ。
同じ子育て期を過ごした仲間たちに、ふと浮かぶ言葉を出してもらった。
「泥んこ」というキーワードが出た時にまず浮かんだのは、さまざまな笑顔。
ある子は塗りたくり、ある子は泥水の飛沫にまみれ、ある子はただただ笑っている。
自分の子ども時代の思い出。
それを次の時代に追体験した思い出。
泥だらけの服に「ウタマロ石鹸」を塗ることも無くなった今、なぜか今度は手を真っ黒にして「泥んこ」の絵を描いている。
あのワクワク感は、変わらぬままで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 「しじま」by Makiko Yano
「しじま」by Makiko Yano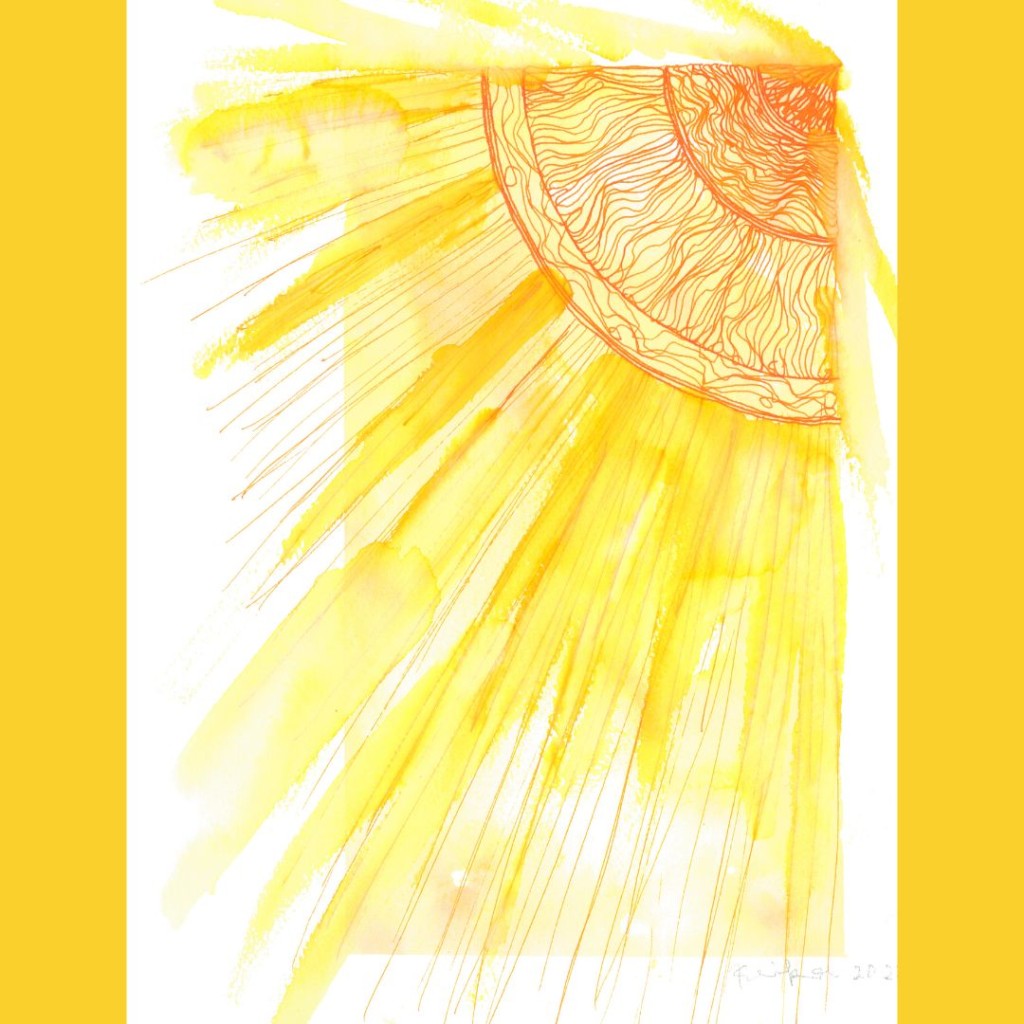

こんな都会で暮らしていながら、本当によく外で遊んでいたもんだ。
末っ子と私は、いつもそれらの付き添いだ。
どちらのスポーツも、練習場所はだいたい砂埃舞うグランドで、暑い夏も寒い冬も、外で過ごす時間が長かった。
「陽だまり」という言葉からは、やはりこの時の光景が連想される。
グランドでは、娘や息子が砂まみれになり、そのグランドの傍で、陽だまりを見つけては、末っ子と遊ぶ。「陽だまり」は常にグランドの砂っぽさとセットなのだ。
練習場所まで連れて行ってくれたり、練習の後一緒に遊んでくれたり。ある時は、練習後お風呂に入れてくれたり。
両親以外の大人と関わることで、心のバランスも取れていたのかなと、今になって思う。
この場を借りて、ありがとう!

うちのリビングには昔、大きな鏡がついていた。
子どもが増えたので自分達の手で工事をした時のこと。リフォームとも言えない内装をざくざくと変えた、とりあえずのスペースを何とか確保するくらいの突貫工事だったが、その部屋になぜか父が一つの壁面いっぱいの大きさの鏡を貼ってくれた。
少しでも部屋が広く見えるように…という心遣いだったのか、子どもたちが遊ぶのに大きな鏡があったらいいと思った所以なのか…真相はわからない。
今回の展示で「なみだ」というお題が出た時、そんな鏡の前で、子どもが大泣きしていたある日のことをふと思い出した。
2人目の子は男子で愛想がよく、小さな頃から愛されキャラで自分自身のことも大好きな子どもだった。その息子、お姉ちゃんと喧嘩してなのか、理由は様々だがよく大きな大きな声を上げて泣いていた。目が大きいのでボロボロと涙が溢れていた。
ある日、大きな鏡の前で泣いている途中でちらっと鏡を覗き、どうやら自分の泣き顔をチェックしている。そしてまた大きな声で泣き始める。もう涙は出ていない。またチェックしてまた泣く。その様子を陰から観察している私に気づくと、今度は大きな声でゲラゲラと笑い始めた。
もう一つは、娘の毎晩毎晩の涙。「龍に乗りたい」と言って泣く。夜中の3時に「肩車して欲しい」と泣く。泣き声が大きくて近所の人に「もしや虐待では」と通報されたこともあるくらい。
でもとことん向き合っているうちに急にそんな日々が終わり、何事もなかったのように成長した。まるで人生の毒出しは、あの涙と共に終わったかのように。
良くもまあ、子どもはたくさん泣き、わたしはその涙を抱きしめ、拭ってきたことか。
そして、圧倒的に子どもに紐づいた涙が多かったように思う。
そしてひとしきり泣いた後は、その理由が何だったのかさえ今では思い出せない。